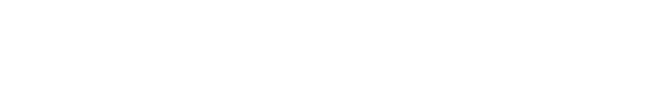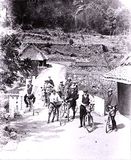自転車から見た戦前の日本
明治から昭和初期にかけての時代、自転車は日本人の生活の中心に入って行きました。
まだ自転車が貴重だった頃、家族そろって記念写真を取るときには、その脇に自転車が置いてありました。
自転車にあこがれていた人たちは自転車レースに夢中になり、レースはやがて小さな子どもから年配の人たちまで広く普及していきました。
その一方で、自転車製造会社から卸商店、小売店までが必死になって自転車を販売したおかげで、やがて人々は自転車で荷物を運んだり、通勤通学に利用したりと自転車を愛用し始め、交通機関の中心となっていきました。
街にでてみると大きな通りには自動車があまり見られず、大半は自転車が走っていましたが、女性が自転車に乗る姿は多くはありませんでした。
こうした自転車を通じて見た戦前の日本の姿を、自転車文化センターが所有する貴重な写真からしることができます。
1. 明治時代(西暦1868~1912年)

別荘地としての軽井沢は明治21年(1888年)、カナダ生まれの宣教師のショーが旧軽井沢に小さな別荘を建てたことに始まる。豊かな自然と清涼な空気に包まれた軽井沢に、友人の宣教師や日本の知識人たちにも絶好の保養地であると紹介し、次第に外国人、財界人、文人、芸術家たちの別荘が増えていった。 明治26年(1893年)には鉄道が開通して町はさらに発展、西洋文化の香り漂う高級別荘地へと生まれ変わっていったが、写真は鉄道開通後の、別荘地として軽井沢の初期の様子を表している。 写真中央の女性がマーガレット・ヤング(名古屋柳城大学創設者)で、女性が自由に自転車に乗るということが考えられない時代でもあった。 (原版は軽井沢土屋写真館)

この当時の女学生は羽織袴姿に、髪は結い流しであった。まだ自転車がステータスシンボルであった頃で、かけそばが1銭8厘のとき、自転車1台が150円~250円と高価であった。
日本人の手による最初の自転車競走は明治29年(1896年)11月上野不忍池畔で大日本双輪倶楽部が催したのが最初で、その後、上野不忍池畔は自転車レースのメッカとなった。レース会場中央には万国旗を吊るし、華族をはじめ花柳界からも多数の観戦者が来場し、大いに盛り上がった。集まった選手は数百名で、競技には子ども競走、提灯競走などもあった。

この頃の自転車店は、自転車そのものの販売は少なく、修繕が主な業務であった。そのため、店主は熟練した鍛冶職人や金物細工のできる時計師などからの転業者が中心であったが、時計店と自転車店を兼業しているところもまだ多かった。

明治33年(1900年)、女性の自転車倶楽部「女子嗜輪会」が誕生した。中央が日本最初のオペラ歌手三浦環である。 彼女は芝の自宅から上野の音楽学校まで毎日、自転車で通学した。当時、女性が自転車に乗ることはほとんどなく、その評判は小説のモデルにまでなった。

横浜アンドリュース・ジョージ商会のボーンや自転車レーサーの鶴田勝三らが自転車にそりをつないで富士山を下った。そりはブレーキの役割を果たした。頂上まで上るときは自転車を担いでいった。

埼玉県志木市にあった蔵作りの朝日屋薬局店頭での記念写真。この当時、自転車を所有していたのはごく一部の富裕層の人たちであった。したがって自転車を所有するということはステータスシンボルの1つであり、写真撮影の際は必ずといっていいほど自転車を脇に置いたものである。

女性が自転車に乗るということがほとんどなかった時代に、日本女子大学を創立した成瀬仁蔵は大学創立当初から自転車部を設け、体育にも自転車を取り入れるなど、女性への自転車普及に人力を尽くした。

明治42年頃から日本橋のデパート三越では、従来徒歩や荷車で行っていた商品の配達に自転車を利用するようになった。この役割を担ったのがメッセンジャーボーイである。白塗りの自転車にハイカラな服装は人目を引いた。松屋も自転車隊を編成するなど、その後他のデパートも自転車で配達するようになった。

明治25年(1892年)頃、イギリス人のボーンが日本で初めて自転車の曲乗りを大阪で披露した。以来、自転車の普及と合わせて、外国人曲乗り師が度々来日したことにより、自転車はサーカスに欠かせない道具の1つとなっていった。
2. 大正時代(西暦1912~1926年)

明治時代の自転車の大半はアメリカ、イギリスからの輸入であったが、明治末期頃から、国内の製造会社が技術力と販売力をつけてきた。その中のひとつ宮田製作所は大正2年(1913年)、当時の逓信大臣元田肇を説いて、従来輸入車のみを使用していた大阪逓信局に国産車を勧め、同製作所のパーソン号に切換えさせた。6月と9月に納入し、以後昭和の初期まで毎年3月、6月、9月の3回に分けて納入していた。

大正時代になると国産自転車の増加とともに、定価も低下し、一般大衆でも手に入れることができるようになってきた。しかし、女性が自転車に乗るということはまだ珍しかった。

明治30年代の自転車レーサーを代表する一人である小宮山長造が引退後、卸店を開設した。その卸店で部品を集めて製作したのがMSA号で、この自転車に乗って長瀞まで遠乗会を実施したときの様子である。

織物業で栄えた足利、桐生、伊勢崎などで織った生地の糊落とし、皺伸ばし、巾揃えなどの工程を行っていた工場である。
右端の自転車は前輪に台車が取り付けられたもので、現代のトラックの役割を果たしていた。大正末期頃から自転車の後ろに取り付けるリヤカーが普及し始め、このような前輪荷台型の自転車は姿を消していった。

丸中商店とあるが、所在地は不明である。写真中央に「逓信局御用」という文字が見える。明治25年(1892年) 、電報配達用として自転車が使われるようになり、これまでの徒歩と較べて配達時間が大幅に短縮される結果となった。このため、翌年には全国4大都市に72両の自転車が配車された
3. 昭和初期(西暦1926~1943年)

昭和初期は不況にも関わらず、自転車の販売は順調に伸び、販売合戦も熱を帯びていた。製造会社代理店による小売店向けの景品付キャンペーンが盛んに行われ、販売台数に応じて抽選本数が小売店に与えられた。景品は「自転車」「桐たんす」「指輪」「かばん」「時計」など実用品が多かった。


自転車の保有台数が大正9年(1920年)は200万台であったのが、5年後には2倍の410万台にまで増加した。この急増に伴い、大正15年(1926年)2月13日、自転車取締まり規則が改正され、登録、車両検査が警察の業務となった。この他、盗難という捜査業務も加わり、警視庁のような世帯の大きな府県警察にとっては大きな負担であった。

昭和3年(1928年)11月、天皇即位式を記念して愛媛県北宇和郡の小学校校庭で町民の自転車レースが行われた。写真はその翌年の春に行われた祝勝会で、3人の芸者が三味線に合わせて即興の踊りを披露している。
写真に写っている自転車は英国製のようで、レースに使われたものである。
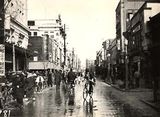
歩道脇に多数の自転車が駐輪してある光景は今と変わらないが、車道に自動車が走っておらず、交通の中心が自転車であったことがわかる。
中央の自転車のハンドル前に荷物を置くための装置が取り付けてあり、当時は自転車が荷物を運搬するための役割を果たしていた。

逓信省御用瀬戸郵便局納入車の看板が見えることから店頭に並んでいるのは納入する宮田製作所のギヤエム号であろう。宮田製作所は昭和2年(1927年)からギヤエム号の発売を始め、昭和7年(1932年)から逓信省に全国の局用車を納入していた。

昭和の時代に入ると、女性の乗輪に対して違和感が消えつつあるときであったので、女性を新たな市場開発の場とした。その一環として、「女性と自転車」の懸賞写真を募集したところ、全国から一千余点の応募があった。この写真が1等の写真である。

戦時体制下に入り、自転車はガソリン不要の乗り物として、戦場はもとより全国各地で動員された若者たちの訓練にも使われた。昭和15年(1940年)に自転車は生産統制が開始し、販売も公定価格となった。
谷田貝一男